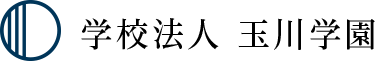研究への支援

夢ではない夢がある事を信じて挑戦するのが「研究」です。
そして、玉川で育まれる個々の夢を形にして叶えた延長線上には「社会貢献」があると信じています。
夢の具現化に向けて研究するのは人であり、その人を育てるのは教育という観点から、研究活動には常に多くの学生たちが参画しています。
皆様からの寄付金を基金に加え、基金の果実を対象分野に利用させていただいており、対象分野は、玉川教育を充実発展させるための諸部門にわたっております。
●学術研究所の研究活動【33】
●脳科学研究所の研究活動【34】
●量子情報科学研究所の研究活動【35】
●教育及び学術上の国際交流【51】
●学術研究者等の人材の養成【52】
●国内外の優れた学識経験者等の招聘【53】
事例紹介
ロボカップ2024世界大会アイントホーフェン(オランダ)参加

2024年7月にオランダ・アイントホーフェンで開催された「RoboCup 2024(世界大会)」において、本学チーム「eR@sers(イレイサーズ)」が生活支援を行う自律型ロボットの性能を競う@Home DSPL(Domestic Standard Platform League)で2位の成績を収めました。
同時に、パーティ会場のような様々な人がいる場面で活躍できるロボットに与えられる特別賞「Soul of the Party」も受賞しました。
また、参加メンバーである工学部情報通信工学科の竹中さん(当時3年)は、2024年12月に開催された計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2024)において、RoboCupにおいて直面した問題を研究テーマに「スマートフォンを用いた生活支援ロボットのための動的物体教示簡易インターフェースの提案」について発表し、「優秀講演賞」を受賞しました。

奄美大島産のタテナシウメマツアリが示す特異な繁殖戦略の解明
本事業では、奄美大島のタテナシウメマツアリにみられる、「働きアリの形をした女王アリ(職型女王)」を研究しました。
本種は四国や九州、沖縄に分布し、他のアリと同様に働きアリよりも大きな女王がいます。しかしながら奄美大島でのみ職型女王が確認されています。そこで2024年9月および2025年2月に奄美大島にてタテナシウメマツアリの巣(コロニー)64個を採集し、その女王形態などを調べました。その結果、それらは通常の形態の女王と働きアリにより構成されるコロニーと、職型女王と働きアリにより構成されるコロニーの2パターンに分かれること、職型女王は多くの部位で働きアリに類似した特徴を示すものの繁殖に関わる特徴は女王に類似の特徴を示すことができ、これらの研究内容を2025年3月に札幌で行われた第72回日本生態学会大会にて発表しました。

台湾・桃園市の3つの幼児園と保育者養成校の視察
台湾・桃園市の3つの幼児園と保育者養成校の視察を行いました。台湾はいち早く幼保一元化を実現し、先駆的な幼児教育の実践が行われています。
今回参観した3園は、幼児期に質の高い教育を行うことを目指し、遊びを中心とした子ども主体の保育が展開されていました。うち2園は山間部の園で、原住民族であるタイヤル族の居住地域でもあり、タイヤル族の伝統的な文化や言語を大切にした保育が行われていました。一方、市の中心部の幼児園では、ICTや英語が保育の中に取り入れられており、異なる保育の様子を見ることができました。
また、幼保一元化をめぐる問題点ついても明らかになり、今後の日本の幼児教育を考える上で、有意義な視察となりました。

NTU先端研究体験および中高生の課題研究コンテストイベント“Global Link Singapore”への参加
2024年7月、シンガポール国立南洋理工大学(NTU)で開催された「Global Link Singapore 2024」に参加しました。これはアジア各国の中高生が集い、自らの研究成果を英語で発表・交流する国際コンテストです。本校からは8名の生徒が参加し、うち1名が「Visualization of Pulmonary Airflow and Analysis of Pathogen Adhesion」という研究で基礎科学部門第2位に入賞しました。現地では、NTU佐藤教授のご協力により、同研究室にてAIや医療応用、ナノテクノロジーを含む最先端技術の体験型講義も実施され、理系のみならず幅広い分野に関心を持つ生徒にとって貴重な刺激となりました。本取り組みは、科学技術と国際性を融合した本校独自のSSH活動として、今後も継続的に発展を目指しています。
玉川学園ホームページ掲載記事はこちら
主な実績
●玉川学園における「全人」「玉川っ子」使用傾向の分類および概念・意味変容の検証
●AERAにて"教員養成における国際協働オンライン学習の効果と課題"の研究発表および米国ウィルクス大学との共同研究の今後の発展に向けた意見交換
●国際共同研究「赤ちゃんの言語習得」
●玉川学園の音楽教育~吹奏楽を通した国際交流の実践~
●学術研究所ICT教育研究センター 開設記念フォーラム開催
●Casa da Musica 及び東京文化会館との教育連携による音楽指導力育成事業
●TAP(Tamagawa Adventure Program)設立20周年記念シンポジウム開催
●ロボカップ2021世界大会で玉川大学チームが優勝
●本物に触れる教育ベルリン・フィル団員と創る教育プログラムの実施
●植物ミトコンドリア遺伝子の発現制御機構の統合的な解明
●「グローバル・アクティブ・ラーニング研究期間2015」開催と講演者の招聘
●玉川大学の教員養成と玉川学園の協働によるプログラミング教育の実践
●玉川大学卒業生に対する「教育内容等の改善充実に関するWeb調査」の実施・分析
●国内外の演劇実践系大学における俳優教育の調査研究とカリキュラム構築
●教師教育を視点にした大学歴史教育改革のための基礎的研究
●玉川学園礼拝堂及び玉川学園チャペルのオルガンを使用したデジタル音源の録音制作
●玉川大学・玉川学園とオレロップ体育アカデミーとの体育教育交流に基づく体操の指導法・補助法及びスポーツに関する指導法の共同研究
●高等教育における我が国の舞台芸術教育方法のスタンダード構築と国際化への学際研究
●ミャンマー連邦国の文化・教育等に関する講演会の開催
●「第10回記念スンマ・クム・ラウデ国際青少年音楽祭ウィーン」への参加
●「第70回 ミッドウエスト・クリニック」への参加
●教員養成課程における学校インターンシップに関する研究
●玉川・HGC教育的交流プロジェクト
●芸術学部生向け特別講演、特別公演、共同研究特別ワークショップ開催
●「ラルフ・ケレンツ講演会 ―新教育の歴史と現在―」開催
●デンマーク・オレロップ体育アカデミーのエリートチーム招聘
●玉川学園とブンデス・スキー・アカデミーとの関係の再構築